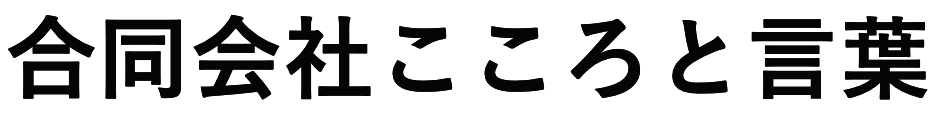豊かな人生、幸せな人生を歩みたい、と思う人は多いと思います。それなりの人生でも大丈夫、と思っている人もいますが、それは言葉の定義次第で結局は「豊かな」人生である、と言い換えることも出来ます。貧しくなりたくない、ちょっとした贅沢でいい、というのも「豊かさ」を求めているということになります。
では、そのために何が必要なのでしょうか。お金、余裕がある時間、恵まれた人間関係など。それこそ、人それぞれ答えがあると思いますが、豊かな人生に絶対的に必要なものが「こころの学び」です。なぜ「こころの学び」が必要かというと、豊かさや幸せを感じるのは頭ではなく、「私たちのこころ」だからです。
一般基準の豊かさや幸せを数値化したものを求めても、幸せにはなりません。100億円あったところで、私たちが何をすればこころが満たされるか、を知らなければ、価値はありません。今回は心理学や哲学の角度から、こころの学びを解説していきます。
1.こころの学びとは?

こころの学びと聞くと大抵の人は心理学を考えるのではないでしょうか。確かに心理学はこころの学びではありますが、心理学者がみんな人生に満足していて、幸せな生活、豊かな生活を送っているか、というと、そうではないと思います。中には心理学は学んでいるものの、思った通りにならず、ストレスを感じる人もいます。ここで言うこころの学びとは、考え方やこころの動きのことです。
認知心理学という心理学がありますが、この心理学でいう「認知」とは物事を知り、判断し、想像・推論したり、決定したり、記憶したり、という様々な要素を含んでいます。分かりやすく伝えるなら、認知とは考え方や捉え方のこと、だと思ってください。こころの学びをしていくことで、この認知能力に幅が出てきます。今までは1つの出来事や経験から1つの感情が反射的に出てくるくらいのレベルでしたが、こころの学びをしていくと、そもそもなぜその感情になるのか、どういった考え方をしているのか、というところに意識が向くため、1つの出来事や経験から複数の感情に意識が向きます。なぜならば、感情とはある種思考によって生まれるものだからです。
ちなみに、感情を英語で言うとemotionという言葉になり、これは同じく英語のmotion(動作)から来たと言われています。動作が感情を作るという説もありますが、ここでは思考が感情に影響を及ぼす、という考え方で進みたいと思います。この節をまとめると、こころの学びをすることで、様々な思考が身に付き、人生が感情に支配されることはなくなり、豊かになる、というところにつながります。
認知心理学という心理学がありますが、この心理学でいう「認知」とは物事を知り、判断し、想像・推論したり、決定したり、記憶したり、という様々な要素を含んでいます。分かりやすく伝えるなら、認知とは考え方や捉え方のこと、だと思ってください。こころの学びをしていくことで、この認知能力に幅が出てきます。今までは1つの出来事や経験から1つの感情が反射的に出てくるくらいのレベルでしたが、こころの学びをしていくと、そもそもなぜその感情になるのか、どういった考え方をしているのか、というところに意識が向くため、1つの出来事や経験から複数の感情に意識が向きます。なぜならば、感情とはある種思考によって生まれるものだからです。
ちなみに、感情を英語で言うとemotionという言葉になり、これは同じく英語のmotion(動作)から来たと言われています。動作が感情を作るという説もありますが、ここでは思考が感情に影響を及ぼす、という考え方で進みたいと思います。この節をまとめると、こころの学びをすることで、様々な思考が身に付き、人生が感情に支配されることはなくなり、豊かになる、というところにつながります。
2.自分の心の動きが分かる

次に、こころの学びをすることで、私たち自身がどのような心の動きをしているか、ということを知ることが出来ます。普段の生活で私たちはなにかしら行動をしていると思います。ある物を選んで食べたり、どこかに遊びに行ったり、何かしらの勉強をしたり、誰かと話したり、といった行動をしています。そして、行動が引き起こすものはなにか、というと結果です。そして、その結果によってまた、感情を動かされ、別の行動をするか、あるいは、行った行動を繰り返すか、を判断し、生活していきます。
motionとemotionの説明とは逆になりますが、大抵の人は意識しない限りは、感情から行動を行っていきます。悲しいときは泣く、といった行動を。楽しいときは笑うといった行動を。怒った時は攻撃的になったり、あるいは、その場から逃げてみたり、と。感情は様々な場面で出てきては、私たちの行動を引き起こしていきます。こころの学びをすることで、私たち自身のこころの動き方が言語化できるようになります。今まではなんとなく、嫌だな、とか、好きだな、とかという判断で日々の生活を送っていましたが、そもそもなぜ好きか、どのような時に、私たちがいい氣持ちになるのか、といったことが理解できるようになると、あとは、私たち自身がいい氣持ちになるような行動をしていくこともできますので、常にいい氣持ちを引き出す行動に意識を向けることができます。これは人生において豊かさを求める人に必要なスキルではないでしょうか。
今の時代は非常に便利なもので溢れています。多くの人はネットを利用できますし、雨風が防げる屋根壁付の家に住み、水道も完備されています。その中で、私たち自身が今、何によって満たされているか、と氣付くことは重要です。そこからさらにより良い氣持ちを目指すには、やはり、私たち自身のこころの動きを知り、どのような時に嬉しくなるのかを、言語化し、認知する必要があります。こころの学びはこういったことにもつながっていきます。
motionとemotionの説明とは逆になりますが、大抵の人は意識しない限りは、感情から行動を行っていきます。悲しいときは泣く、といった行動を。楽しいときは笑うといった行動を。怒った時は攻撃的になったり、あるいは、その場から逃げてみたり、と。感情は様々な場面で出てきては、私たちの行動を引き起こしていきます。こころの学びをすることで、私たち自身のこころの動き方が言語化できるようになります。今まではなんとなく、嫌だな、とか、好きだな、とかという判断で日々の生活を送っていましたが、そもそもなぜ好きか、どのような時に、私たちがいい氣持ちになるのか、といったことが理解できるようになると、あとは、私たち自身がいい氣持ちになるような行動をしていくこともできますので、常にいい氣持ちを引き出す行動に意識を向けることができます。これは人生において豊かさを求める人に必要なスキルではないでしょうか。
今の時代は非常に便利なもので溢れています。多くの人はネットを利用できますし、雨風が防げる屋根壁付の家に住み、水道も完備されています。その中で、私たち自身が今、何によって満たされているか、と氣付くことは重要です。そこからさらにより良い氣持ちを目指すには、やはり、私たち自身のこころの動きを知り、どのような時に嬉しくなるのかを、言語化し、認知する必要があります。こころの学びはこういったことにもつながっていきます。
3.相手の求めていることが分かる

最後にこころの学びは相手の求めていることを理解しやすくもなります。ご存知の通り私たち1人1人は違います。同じ人間であっても私と全く同じ考え方、価値観を持っていて、感じ方まで一緒という人はいません。そして、この「違い」は特に悪いことではないのですが、違うことで問題も起きます。
例えば「未知」という言葉を聞くとどう思いますか?ある人は好奇心を抱くかもしれません。昨今の「コロナウイルス」というものは感染が拡大し始めた頃は「未知のウイルス」として認識していた人もいると思います。基本的に「知らない」ということは人のこころから、ちょっと怖いな、という氣持ちを引き起こしやすいです。自分とは違ってるから、というのは、この「未知」という言葉が抱かせる感情に近いです。
人は違いを感じるととるべき行動は3つ。排除する、直そうとする、知ろうとする、です。
まずは排除。これは、私たち自身と違う者への共存をともかく拒み、今の私たちの安全地帯を守ろうとする心理です。別に違う相手が悪い訳ではないんです。ただただ、怖いんです。恐怖が引き起こす感情に攻撃性がありましたね。それです。
そして次に、直そうとすること。今の私たちと違うので、何か壊れてるんじゃないのか、と思い、今の私たちに近付けようとします。育成などがこの感覚に近いです。こうするといいよ、こう考えたら楽になるんじゃない、というようなアドバイスという形を取り、相手の考え方や感じ方を直そうとします。
最後に知ろうとする、です。私たちと違うから、どう違うのかを考えます。そのときに必要となるのが、こころの学びです。心理学とはそもそも科学的な手法をとり、心と行動の関連性を調べていくデータを基にした学問です。知ろうとするときに、心の特徴や行動特性という「一般規定」のようなものがあると、違いを理解しやすく、参考にすることができます。そして、私たちとの違いが明確になれば、相手にとって大切なことも分かる様になり、円滑な人付き合いが出来るようになります。
こころの学びの中に心理学がある、というイメージですが、この分かろうとすることが必要です。その過程で、心理学を使う、ということになると思います。もちろんここでも決めつけは危険なので、目の前の相手をきちんと想うということが重要になります。つまり、違いを知るために、こころの学びの中の一分野である心理学を学ぶことが役に立つ、という認識です。
例えば「未知」という言葉を聞くとどう思いますか?ある人は好奇心を抱くかもしれません。昨今の「コロナウイルス」というものは感染が拡大し始めた頃は「未知のウイルス」として認識していた人もいると思います。基本的に「知らない」ということは人のこころから、ちょっと怖いな、という氣持ちを引き起こしやすいです。自分とは違ってるから、というのは、この「未知」という言葉が抱かせる感情に近いです。
人は違いを感じるととるべき行動は3つ。排除する、直そうとする、知ろうとする、です。
まずは排除。これは、私たち自身と違う者への共存をともかく拒み、今の私たちの安全地帯を守ろうとする心理です。別に違う相手が悪い訳ではないんです。ただただ、怖いんです。恐怖が引き起こす感情に攻撃性がありましたね。それです。
そして次に、直そうとすること。今の私たちと違うので、何か壊れてるんじゃないのか、と思い、今の私たちに近付けようとします。育成などがこの感覚に近いです。こうするといいよ、こう考えたら楽になるんじゃない、というようなアドバイスという形を取り、相手の考え方や感じ方を直そうとします。
最後に知ろうとする、です。私たちと違うから、どう違うのかを考えます。そのときに必要となるのが、こころの学びです。心理学とはそもそも科学的な手法をとり、心と行動の関連性を調べていくデータを基にした学問です。知ろうとするときに、心の特徴や行動特性という「一般規定」のようなものがあると、違いを理解しやすく、参考にすることができます。そして、私たちとの違いが明確になれば、相手にとって大切なことも分かる様になり、円滑な人付き合いが出来るようになります。
こころの学びの中に心理学がある、というイメージですが、この分かろうとすることが必要です。その過程で、心理学を使う、ということになると思います。もちろんここでも決めつけは危険なので、目の前の相手をきちんと想うということが重要になります。つまり、違いを知るために、こころの学びの中の一分野である心理学を学ぶことが役に立つ、という認識です。
4.向き合うことで豊かな人生が送れる

前項目でお伝えした、違いを理解するための学門としての心理学ですが、違いは理解すれば終わり、という訳ではありません。違うんだ、と分かったのであれば、違いと向き合う必要があります。その向き合い方で必要となってくるのが、物事の考え方である、西洋哲学や東洋古典の中にある物事の捉え方です。
歴史を学んでいくと、人間の本質はさほど変わっていないことが分かります。今は物が満たされているため、どうしてもこころに氣付きにくくなっているようですが、幸せや豊かさは物ではなく、私たちのこころの中にあります。そして、そのこころを動かすヒントが哲学や古書にあるのです。
例えば、言志四録の中にある、『富を欲するの心は即ち貧なり。貧に安ずるの心は即ち富なり』という言葉があります。これは心理学でもなんでもなく、考え方です。意味合い的には、欲には際限がなく、欲する心は貧しい。足るを知れば、それこそが富である、というものです。どうでしょう。この考え方は生き方のヒントになりませんか。もちろん人それぞれ違うので、この考え方がヒントになる人もいれば、まったくならない人もいます。それに、私たちの環境によっても考え方が変わっていくものなので、同じ言葉でも、聞くタイミングが違えば、同じ言葉なのに、違う意味を感じることもあるでしょう。
つまり、こころの学びは、日頃の学びや体験を通じ、知っていくことがスタートで、その知ったことと向かい合い、受け容れることで、より良い豊かさを味わえる、ということにつながっていきます。
歴史を学んでいくと、人間の本質はさほど変わっていないことが分かります。今は物が満たされているため、どうしてもこころに氣付きにくくなっているようですが、幸せや豊かさは物ではなく、私たちのこころの中にあります。そして、そのこころを動かすヒントが哲学や古書にあるのです。
例えば、言志四録の中にある、『富を欲するの心は即ち貧なり。貧に安ずるの心は即ち富なり』という言葉があります。これは心理学でもなんでもなく、考え方です。意味合い的には、欲には際限がなく、欲する心は貧しい。足るを知れば、それこそが富である、というものです。どうでしょう。この考え方は生き方のヒントになりませんか。もちろん人それぞれ違うので、この考え方がヒントになる人もいれば、まったくならない人もいます。それに、私たちの環境によっても考え方が変わっていくものなので、同じ言葉でも、聞くタイミングが違えば、同じ言葉なのに、違う意味を感じることもあるでしょう。
つまり、こころの学びは、日頃の学びや体験を通じ、知っていくことがスタートで、その知ったことと向かい合い、受け容れることで、より良い豊かさを味わえる、ということにつながっていきます。
5.まとめ
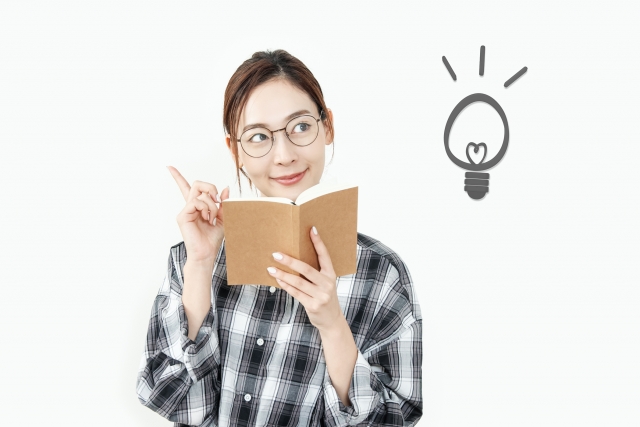
こころの学びが人のこころと人生を豊かにするのは、次の流れになります。まず、認知の幅を広げ、変えることにつながります。認知をすることで、自分の考えや氣持ちを知り、さらに、人間関係の中の違いを認め、相手の求めることが分かるようになります。そして、そうした体験の繰り返しの中で、認め、受け容れ、豊かになっていくという流れをとっています。
逆にこころの学びを全くしなければ、認知の幅が広がらないので、今の考え方から出にくくなり、日々変わっていく、生活の中に新しさを取り入れられないことになり、次第に窮屈になり、窮屈さから逃れるために、答えを内側ではなく、外側に求め、責任も周りに求めるようになります。
しかし、そこでも外側の教育には、「人のせいにしない」というルールがありますので、ただただ耐える、というところになり、豊かさとは遠い生き方になる可能性もあります。まずは、知るところからスタートしてみてはどうでしょうか?
逆にこころの学びを全くしなければ、認知の幅が広がらないので、今の考え方から出にくくなり、日々変わっていく、生活の中に新しさを取り入れられないことになり、次第に窮屈になり、窮屈さから逃れるために、答えを内側ではなく、外側に求め、責任も周りに求めるようになります。
しかし、そこでも外側の教育には、「人のせいにしない」というルールがありますので、ただただ耐える、というところになり、豊かさとは遠い生き方になる可能性もあります。まずは、知るところからスタートしてみてはどうでしょうか?