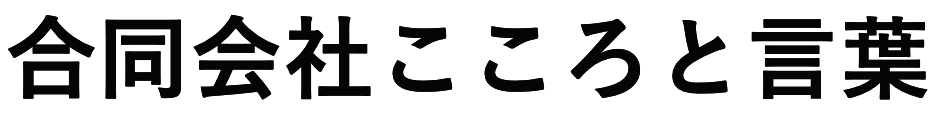カウンセリングをしていると自然と悩みがある人が相談という形でお話に来てくれます。人の悩みを聞くことを主な仕事にしていると周りから言われることが2つ。
・悩みを聞くのってこっちまで気が滅入らない?という思いやりの言葉。
・悩みを聞いてそれだけで仕事になるっていいねという楽観的なもの。
もちろんどちらの側面もあるかと思いますが、心理家の悩みの捉え方が根本的に違うと最近気付いたので、今悩みを抱えた人に届けたい心理学的な成長の6ステップとして「悩みベースの考え方」をお伝えします。いつも悩んでいる、同じことに悩んでいる、悩みとは捉え方であるとは頭で理解していても体現できていない、という人は悩みの進化系のカタチを知るだけでも考え方が変わると思います。
新しい悩みのカタチとは?考え方を売る店として一つの考え方をお伝えします。
1.悩みの種

「○○についてこうなればいいんだけど」とか「○○がなければこうできるのに」と言った悩みはありますか?あるいは自分に向けて「私はどうしていつもこうなんだろう」といった悩みもあるかもしれません。そもそも「悩み」とは何か?と考えてみるとあまりいいイメージはありません。ネットで調べてみても悩み=精神的に苦痛・負担を感ずること。そう感じさせるものとあります。
つまり悩みがある状態はメンタル的にも良くはないのです。悩みがない方がいいとも言えます。しかし、その捉え方が少し違うのです。悩んではいけない、ではなく、悩んでいる状態は必ず終わりが訪れるという捉え方が適切です。問題は、どのようにしたら悩みは終わるのか?ということです。それが悩みの進化系、問題という形です。
私たちは義務教育からも「問題を与えらえると回答を考える」というある種、 反射的な思考を手に入れています。その解答が分かる、分からないは別として、問題があれば、考えようとするという事実を知っておきましょう。そのため悩みを終焉に向かわせるためには悩みを問題にするというステップが必要になります。ただの悩みからあなたの問題へと進化させるのです。悩みが悩みであるためには思考のプロセスを入れてはいけません。
「悩み」に「思考」が入ると「問題」になります。このステップを理解しておきましょう。
つまり悩みがある状態はメンタル的にも良くはないのです。悩みがない方がいいとも言えます。しかし、その捉え方が少し違うのです。悩んではいけない、ではなく、悩んでいる状態は必ず終わりが訪れるという捉え方が適切です。問題は、どのようにしたら悩みは終わるのか?ということです。それが悩みの進化系、問題という形です。
私たちは義務教育からも「問題を与えらえると回答を考える」というある種、 反射的な思考を手に入れています。その解答が分かる、分からないは別として、問題があれば、考えようとするという事実を知っておきましょう。そのため悩みを終焉に向かわせるためには悩みを問題にするというステップが必要になります。ただの悩みからあなたの問題へと進化させるのです。悩みが悩みであるためには思考のプロセスを入れてはいけません。
「悩み」に「思考」が入ると「問題」になります。このステップを理解しておきましょう。
2.問題の種類

前の項目で悩みは思考を経て問題になりました。問題になると何となくですが、悩みの状態よりもはっきりと言語化できていたり、様々な種類のものに分解されていたりします。しかし、問題を多く抱えた状態では、まだストレスのままです。悩みとさほど変わらない、と思われる方もいるかもしれません。そこで、その問題をまず目の前に並べるために、書きだしてみましょう。数多くの問題が目の前に並びます。
そして、次に問題の進化が必要です。そのためには 「選択」という過程・解決策を入れる必要があります。数ある問題の中から3つ、あるいは多くとも7つだけ解決するとすれば、どれが一番効果的か、ということを選びます。問題に選択という過程が入ると次のステップになっていきます。様々な種類があり、自分でなんとかできるもの、自分では何ともできないもの、環境的な要因や内部的な思考の問題などなど。
ここで大切なのは実は問題は問題ではありません。問題を問題だと思うことが問題なのです。そのため、3つから7つ解決できるものを選ぶことが出来たら、「問題」は次のステップ「課題」に進化します。
そして、次に問題の進化が必要です。そのためには 「選択」という過程・解決策を入れる必要があります。数ある問題の中から3つ、あるいは多くとも7つだけ解決するとすれば、どれが一番効果的か、ということを選びます。問題に選択という過程が入ると次のステップになっていきます。様々な種類があり、自分でなんとかできるもの、自分では何ともできないもの、環境的な要因や内部的な思考の問題などなど。
ここで大切なのは実は問題は問題ではありません。問題を問題だと思うことが問題なのです。そのため、3つから7つ解決できるものを選ぶことが出来たら、「問題」は次のステップ「課題」に進化します。
3.課題の質
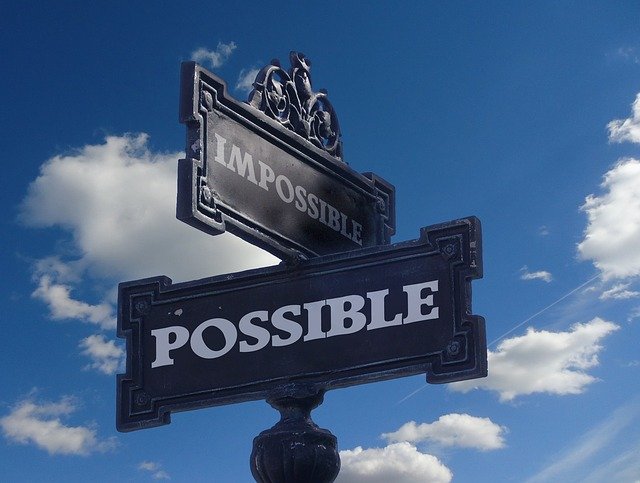
「悩み」は「思考」というプロセスを経て「問題」になりました。そして、「問題」を「選択する」というプロセスを経てこの「課題の段階」にきます。出てきた課題を見ていくと、だんだんと悩みから遠ざかったような気がします。課題であるからには不可能なものは入れてはいけません。可能なものにフォーカスしています。
そして、課題になったら次の要素を入れていきます。それが「計画」というものです。計画には、課題の質の選定が必要となりますが、その中には自分が理想とする映像やイメージをする必要があります。もともと悩みは不満や不安があったということなので、何に対する、という対象があります。 対象の変化を望んで、初めて悩みは生まれるものなので、この課題の段階でもう少し明確に望みをイメージしていきましょう。どうなって欲しいか、あるいはどうなりたいか、というイメージをしながら、問題の中から真の課題を1つ(多くて3つ)に絞り、計画を立てていきます。
「課題」に「計画」が入ってくると、いよいよ次のステップにいきます。この時点で、課題に計画を付け加えますが、付け加える計画は2点必要です。
1つ目は第三者が分かる基準です。例えば、ビックになるというもの。どのようになればビックになったかは分かりません。CDを出す、YouTubeチャンネルを開設する、登録者を100名にするなど、第三者からみて分かる基準を付けておきましょう。
もう1つが期限です。上の例でいえば、いつまでにCDを出すのか、いつまでに登録者数を100名にするのか、など期限があることが必要です。期限がない課題は、実は問題のままなのです。
そして、課題になったら次の要素を入れていきます。それが「計画」というものです。計画には、課題の質の選定が必要となりますが、その中には自分が理想とする映像やイメージをする必要があります。もともと悩みは不満や不安があったということなので、何に対する、という対象があります。 対象の変化を望んで、初めて悩みは生まれるものなので、この課題の段階でもう少し明確に望みをイメージしていきましょう。どうなって欲しいか、あるいはどうなりたいか、というイメージをしながら、問題の中から真の課題を1つ(多くて3つ)に絞り、計画を立てていきます。
「課題」に「計画」が入ってくると、いよいよ次のステップにいきます。この時点で、課題に計画を付け加えますが、付け加える計画は2点必要です。
1つ目は第三者が分かる基準です。例えば、ビックになるというもの。どのようになればビックになったかは分かりません。CDを出す、YouTubeチャンネルを開設する、登録者を100名にするなど、第三者からみて分かる基準を付けておきましょう。
もう1つが期限です。上の例でいえば、いつまでにCDを出すのか、いつまでに登録者数を100名にするのか、など期限があることが必要です。期限がない課題は、実は問題のままなのです。
4.行動の焦点

「課題」に「計画」が入るといよいよ行動のステージです。もうこのステージに来ると悩みは見当たりません。ちなみに脳内の変化としては分からないから不安が起こるのであり、不安だから分からないというものではありません。 私たちは分からないものを、ここまでのステップで課題にまで昇華してきました。もう不安は少なくなっています。なぜなら「分かっているから」からです。分かっているなら動くだけなのですが、普段はなかなか動けません。そのため、課題のステージで計画を入れたのです。計画通りに動きましょう。どうしても計画がしっかりしていないと行動が雑になってきます。目の前の提案が魅力的であったり、楽そうだったり、手っ取り早いものだったりします。当初立てた計画は貫く必要があります。
そこで、行動の中に意思決定の言語化というものを入れます。これは何かというと迷ったら戻ってくるというものです。例えば、1年後の幸せであったり、5年後の笑顔であったりします。本当にそれで1年後の幸せになれるか、5年後の笑顔につながるか、と考えておきます。もし、行動をしていて迷ったら、この「意思決定」が入ることでようやく、行動は次のステージの結果に繋がっていきます。
そこで、行動の中に意思決定の言語化というものを入れます。これは何かというと迷ったら戻ってくるというものです。例えば、1年後の幸せであったり、5年後の笑顔であったりします。本当にそれで1年後の幸せになれるか、5年後の笑顔につながるか、と考えておきます。もし、行動をしていて迷ったら、この「意思決定」が入ることでようやく、行動は次のステージの結果に繋がっていきます。
5.結果を学ぶ
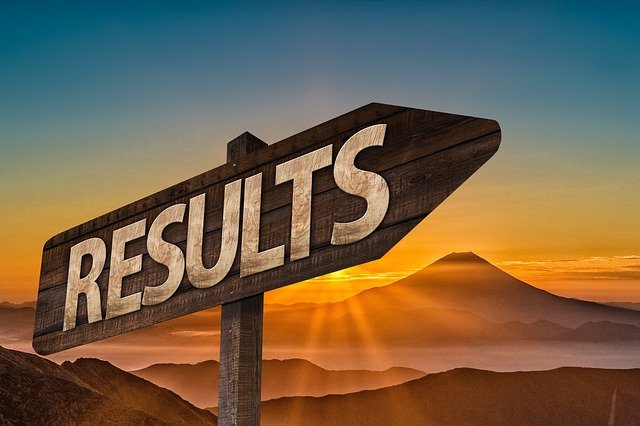
「行動」に「意思決定の基準(言語化)」がきちんと入ると結果につながります。もちろん結果は絶対的についてくるものです。システムの言葉でGI/GOという言葉があります。Garbage in, garbage outということで、意味のない入力からは意味のない結果しかでないということです。結果はどのようなものからでも出ます。収入が変わらず、使うお金が増える、という行動をするとお金が減るという結果に。人の悪いところを高圧的な態度で指摘し続ける、という行動をすれば、人から嫌われるという結果が。つまり行動をすると結果は出ますが、この結果に対して、「チェック」というものをしなければいけません。GI/GOという法則に立ち返り、「あれ??ゴミみたいな結果になったぞ」ということであれば、GIの部分である、間違った行動をしていたことになります。「課題」に「計画」を入れたことで「行動」にはなりました。そして、「行動」に「意思決定」を入れたので「結果」は出ました。しかし、 まだなんか違うな、ということであれば、「計画」か「意思決定」が違ったということになります。この「チェック」をするところをしっかりしていくと、結果は次第に次のステップ、「成果」に繋がっていきます。結果で終わることなく「チェック」という項目を入れて「成果」を目指していきましょう。
ちなみにチェックとは数値化されているものが望ましいです。チェックが曖昧であれば、結果に対してのアプローチが異なってきますので、チェックをしっかりする、という定性的な判断ですることがないように定量的なシステムを作っていきましょう。
ちなみにチェックとは数値化されているものが望ましいです。チェックが曖昧であれば、結果に対してのアプローチが異なってきますので、チェックをしっかりする、という定性的な判断ですることがないように定量的なシステムを作っていきましょう。
6.本当の成果とは

「結果」に「チェック」が入ってようやく「成果」が手に入ります。これが悩みの最終ステージです。成果の定義をしておきます。 成果とは、自分の望むべきゴールのことです。これは課題のところでも出ましたが、私たちが本当に達成したいものは結果ではなく成果なのです。そして、 成果を上げるにはたくさんの結果が必要となります。しかし、多くの人は結果を求めているから、結果が手に入らないのです。本当に手に入れたいたった1つの成果を求めて行動すると、多くの結果が入ってきます。それはお金であったり、たくさんの思いやり溢れる人脈であったりします。
金メダルを取るような水泳のオリンピック選手の方に行ったインタビューを昔見たことがあります。誰よりも早く一番に、、、という結果を求めてはいないそうです。求めているのはゴールテープのさらに先に届くイメージだそうです。早くゴールに着くではなく、ゴールの先に手を伸ばすイメージで練習、試合に臨むと必然的に一番になることが多いようです。求めるのは結果ではなく、成果。成果を出すためにはたくさんの結果がついてくる。1つだけ求める成果は何になりますか?結果をチェックしながら1つの成果を目指していきましょう
金メダルを取るような水泳のオリンピック選手の方に行ったインタビューを昔見たことがあります。誰よりも早く一番に、、、という結果を求めてはいないそうです。求めているのはゴールテープのさらに先に届くイメージだそうです。早くゴールに着くではなく、ゴールの先に手を伸ばすイメージで練習、試合に臨むと必然的に一番になることが多いようです。求めるのは結果ではなく、成果。成果を出すためにはたくさんの結果がついてくる。1つだけ求める成果は何になりますか?結果をチェックしながら1つの成果を目指していきましょう
7.まとめ

いかがでしたか?もとは「悩み」から始まった6つの階段。悩み、問題、課題、行動、結果、成果というステージ。一番お伝えしたいことは、理想の成果も最初は悩みだったということです。つまり、悩みは成果の種なのです。もし今、あなたが悩み多いステージで常にキツイということであれば、 すさまじい成果を上げる可能性が誰よりも高いということです。落とし穴として、 悩むことに悩んでいたら、負のループにハマってしまいます。きちんと悩みを人間的な成長のステップとして上げるためにこの6ステップを意識して、より良い成果(生き方)を求めて、まずは悩みに思考を入れて、問題にしてみてくださいね。
メルマガ登録・講座案内は↓↓
メルマガ登録・講座案内は↓↓