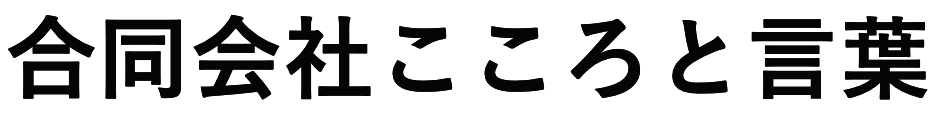日常生活で話し方を学んだことがある人はどれくらいいるでしょうか。気が付いたら話していて、なんとなく会話をしている、と思っている人がほとんどではないでしょうか。学ぼうとして、人を操る心理術、思い通りに動かす話し方、など心理学をベースとしたいわゆる心理話術から学ぶ人もいます。しかし、たくさん学んだからといって理想通りの人間関係が築けるか、というとそうでもない気がします。
人の心を主として話し方を工夫していても、その話す内容が伝わらなかったり、相手に不快感を与えてしまっては元も子もありません。まずは目的を整理して、なぜ話し方を学んでいるのか、と言うところを明確にしなければなりません。
そこで今回は心理家が心理学を学ぶ上で気を付けることをお伝えし、どのように活用していけばいいのか、というところをお伝えしていこうと思います。
1.スキルしか解説がない

まず心理的なことを学ぼうとするときは大抵の場合、既にトラブルが起こっている時か、タイトルやセミナー名が気になる内容です。
そのため学ぶ動機としては「現在起こっている問題の解決策」か「好奇心」が大きな理由になります。そして、現在起こっている問題の解決策を求めると、大抵はスキル重視の心理にいきます。例えば、このように言ったら、こうなります。というもの。これはスキルの解説書であり、人間関係は学び手それぞれにあります。
今までの積み重ねが人間関係を作り、今の状態が問題ということです。例えば、今まで相手に対し、不信感や尊敬の念を抱かず接していた人がいきなりスキルを使うとどうなるでしょうか。もちろんあまり効果はありません。そのためスキルしか解説がない内容は極力避けます。
同様に好奇心から学ぶと、学べることはあるけど使うことは少なくなります。知識は使わないと大抵は忘れてしまいますので、学ぶ時間がもったいない、と言うことに繋がりますので、興味はあるけど困ってない、という方はまず、どこのシーンで使うか、を決めてから学び始める必要があります。
学びにはジャストインケース、ジャストインタイムがあります。その時が来たら役に立つもの。今学ぶべき必要があるもの。この2つを意識するといい方向で学べると思います。
そのため学ぶ動機としては「現在起こっている問題の解決策」か「好奇心」が大きな理由になります。そして、現在起こっている問題の解決策を求めると、大抵はスキル重視の心理にいきます。例えば、このように言ったら、こうなります。というもの。これはスキルの解説書であり、人間関係は学び手それぞれにあります。
今までの積み重ねが人間関係を作り、今の状態が問題ということです。例えば、今まで相手に対し、不信感や尊敬の念を抱かず接していた人がいきなりスキルを使うとどうなるでしょうか。もちろんあまり効果はありません。そのためスキルしか解説がない内容は極力避けます。
同様に好奇心から学ぶと、学べることはあるけど使うことは少なくなります。知識は使わないと大抵は忘れてしまいますので、学ぶ時間がもったいない、と言うことに繋がりますので、興味はあるけど困ってない、という方はまず、どこのシーンで使うか、を決めてから学び始める必要があります。
学びにはジャストインケース、ジャストインタイムがあります。その時が来たら役に立つもの。今学ぶべき必要があるもの。この2つを意識するといい方向で学べると思います。
2.脳科学を信じすぎない
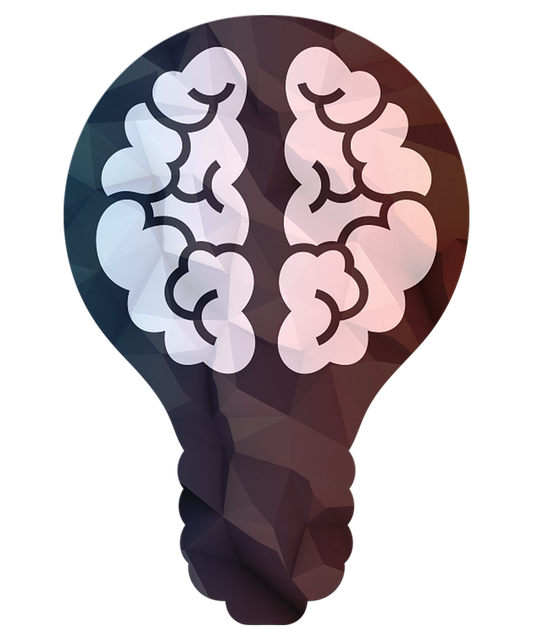
人間の脳について学ぶことは人を理解する上で必要なことです。それはイメージができやすいからです。例えば、磁気共鳴イメージング(MRI)で脳の動きや変化を観察した結果・・・、から始まる言葉や、セロトニンやオキシトシンといった脳内ホルモン・・・、爬虫類脳、哺乳類脳、人間脳・・・という脳の役割での名称・・・。これらは脳科学としての分野にはなりますが、基本的には納得を求めるものであったり、知識を増やしたりする以外の役割はあまりないと考えています。
心理家が求めているのは解決策や改善策であるため、ある程度は脳科学により相手を見ることも必要ですが、脳の役割を理解したところで、相手の行動や私たちの抱えている問題が改善するわけでもありません。
例えば、美味しいカレーが食べたいと思って、カレーの作り方を学ぶだけで終わる、というものです。作らないといけないし、作ったら口に運び味わうということが必要になります。料理で例えると、それは作ったら食べるよ、という意見も聞こえてきますが、脳科学は知識的な欲求が満たされて、それで終わりになるケースが多いのです。「セロトニンは脳を活発にする働きや精神を整える役割があります。セロトニンが多い人は幸せで活動的な毎日を送っています」と学び、そうなんだとなって、次に「セロトニンを増やすには日光や運動が効果的です」と学び、よし早速といってもすぐに整う訳ではありません。とすると学んだことが無駄になりがちです。
脳科学は強力なジャストインケースな学びとして位置付けています。
心理家が求めているのは解決策や改善策であるため、ある程度は脳科学により相手を見ることも必要ですが、脳の役割を理解したところで、相手の行動や私たちの抱えている問題が改善するわけでもありません。
例えば、美味しいカレーが食べたいと思って、カレーの作り方を学ぶだけで終わる、というものです。作らないといけないし、作ったら口に運び味わうということが必要になります。料理で例えると、それは作ったら食べるよ、という意見も聞こえてきますが、脳科学は知識的な欲求が満たされて、それで終わりになるケースが多いのです。「セロトニンは脳を活発にする働きや精神を整える役割があります。セロトニンが多い人は幸せで活動的な毎日を送っています」と学び、そうなんだとなって、次に「セロトニンを増やすには日光や運動が効果的です」と学び、よし早速といってもすぐに整う訳ではありません。とすると学んだことが無駄になりがちです。
脳科学は強力なジャストインケースな学びとして位置付けています。
3.親しみがもてない
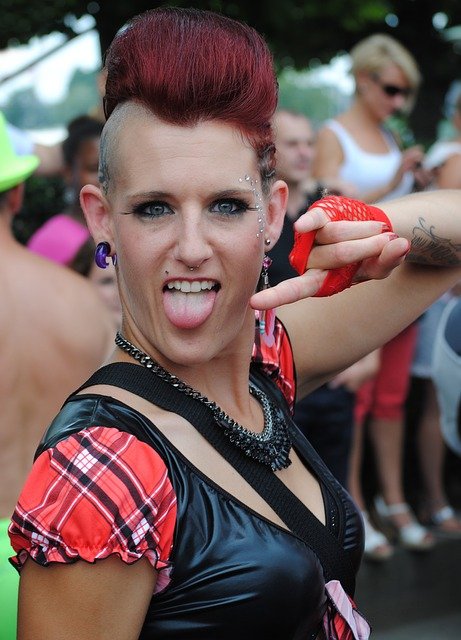
最後は教えてくれる人に対して親しみが持てない場合です。本であれ、セミナーであれ、伝えてくれる人を大事にしています。心理学だけ学んでいると、「誰が言うか、ではなく何を言うか」というところを重視しないと合理的な判断ができない、と言われていますし、その通りだとも思います。
しかし、人の心理を扱う人の心理状態って大切だと考えています。善し悪しの判断ではないのですが、適切か不適切の判断はする必要がある訳です。例えば、私が単4電池2本で動く人だとします。しかし、教えてくれる人は単2電池を持っていて、こちらの方が馬力が強いよ、と進めてくるのですが、合わないんです。単2電池が良い悪いではなくて、この場合は不適切というところになります。その判断基準の1つとして、親しみが持てない、というところです。
言っていることはあってるし、実際その通りなのですが、、、。私自身は「人の心」携わるので、合う合わない理由ははっきりしてます。プロファイリングはできるので、、そのため、合わせることもできなくはないのですが、どうしても窮屈さは残ってしまいます。そのため話すことを仕事としている人が学ぶ心理学の中には、「人」で選ぶことも必要だと考えています。
しかし、人の心理を扱う人の心理状態って大切だと考えています。善し悪しの判断ではないのですが、適切か不適切の判断はする必要がある訳です。例えば、私が単4電池2本で動く人だとします。しかし、教えてくれる人は単2電池を持っていて、こちらの方が馬力が強いよ、と進めてくるのですが、合わないんです。単2電池が良い悪いではなくて、この場合は不適切というところになります。その判断基準の1つとして、親しみが持てない、というところです。
言っていることはあってるし、実際その通りなのですが、、、。私自身は「人の心」携わるので、合う合わない理由ははっきりしてます。プロファイリングはできるので、、そのため、合わせることもできなくはないのですが、どうしても窮屈さは残ってしまいます。そのため話すことを仕事としている人が学ぶ心理学の中には、「人」で選ぶことも必要だと考えています。
4.おススメの学び方

以上を踏まえておススメの学び方をまとめると、自分が好感・親しみが持てるような人(もしくはフラットな姿勢で学べる人)で、根拠が脳科学・統計学・心理学以外にも様々なことを教えてくれる人・内容で、スキル以外の体験談があるもの、となります。
この全てをカバーできるものはあるのか、と考えた時に、本の場合は歴史ある名著ということになりました。例えば「人を動かす」とか「7つの習慣」「思考は現実化する」とかです。他にもアドラー心理学やフランクルなどありますが、出版された年が古いものを選ぶのがポイント。そして、じっくりと時間をかけて読むということ。特に人を動かすや7つの習慣はそれ自体が目次で分けられており、1つだけやれば結果が出ると思わないことです。
例えば、7つの習慣は「主体的」「エンドを描く」「優先事項」「相互利益」「理解する」「総和」「自身を鍛える」の7つからなっておりますが、その中の主体的に動こう、というところだけフォーカスが当たって、それだけをし続けることがないようにしましょう。あくまでも7つの習慣なので、全部する必要があります。しかし、歴史ある心理学者の主張は学び始めると主張者によって違うことが多々あります。褒めたら良い、というものと、褒める行為は相手を下に見る行為だと言っている方もいます。その辺は適切か不適切かは私たち自身で決めていきましょう。もともと心理学に当て嵌めるのではなく、自分や相手を理解して、向上していくための学門だと思っているので、知識にとらわれ過ぎても本末転倒になりますからね。
この全てをカバーできるものはあるのか、と考えた時に、本の場合は歴史ある名著ということになりました。例えば「人を動かす」とか「7つの習慣」「思考は現実化する」とかです。他にもアドラー心理学やフランクルなどありますが、出版された年が古いものを選ぶのがポイント。そして、じっくりと時間をかけて読むということ。特に人を動かすや7つの習慣はそれ自体が目次で分けられており、1つだけやれば結果が出ると思わないことです。
例えば、7つの習慣は「主体的」「エンドを描く」「優先事項」「相互利益」「理解する」「総和」「自身を鍛える」の7つからなっておりますが、その中の主体的に動こう、というところだけフォーカスが当たって、それだけをし続けることがないようにしましょう。あくまでも7つの習慣なので、全部する必要があります。しかし、歴史ある心理学者の主張は学び始めると主張者によって違うことが多々あります。褒めたら良い、というものと、褒める行為は相手を下に見る行為だと言っている方もいます。その辺は適切か不適切かは私たち自身で決めていきましょう。もともと心理学に当て嵌めるのではなく、自分や相手を理解して、向上していくための学門だと思っているので、知識にとらわれ過ぎても本末転倒になりますからね。
5.まとめ

スキルだけ、脳科学に偏り過ぎている、親しみ、というところに注意はしますが、最後に心理学を学ぶというマインドの部分をお伝えします。それは、枠を固めないということになります。
時代は変わっているので、スキルメインの心理学はどうしても適さないことになります。例えばフットインザドアとは簡単な要求からしていき、最後には本当に伝えたいことを伝える心理的なスキルになりますが、そこかしこで使われているスキルなので、「タダほど怖いものはない」という言葉も生まれています。つまり、スキルを学ぼうとするのではなく、心を学ぶ、知る必要があります。
心が傷付くとはどういう状態か、その行動を取る人の心の状態はどのようなものか、さらにその心の在り方はどのようにしてできてきたのか、を「考えるヒントとして」の心理学であると捉えています。そこが「ゴール」ではないです。学んで、話して私たちの生活や人生が少しでも良くなるために、ご活用ください。
↓↓
時代は変わっているので、スキルメインの心理学はどうしても適さないことになります。例えばフットインザドアとは簡単な要求からしていき、最後には本当に伝えたいことを伝える心理的なスキルになりますが、そこかしこで使われているスキルなので、「タダほど怖いものはない」という言葉も生まれています。つまり、スキルを学ぼうとするのではなく、心を学ぶ、知る必要があります。
心が傷付くとはどういう状態か、その行動を取る人の心の状態はどのようなものか、さらにその心の在り方はどのようにしてできてきたのか、を「考えるヒントとして」の心理学であると捉えています。そこが「ゴール」ではないです。学んで、話して私たちの生活や人生が少しでも良くなるために、ご活用ください。
↓↓