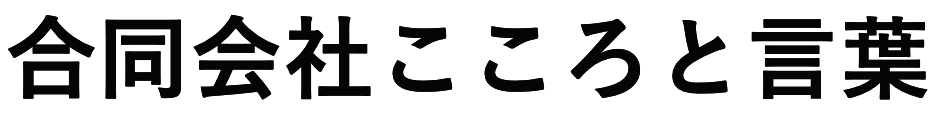先日、夢を語ったところ、それは夢であって現実をもっと考えた方が良いと言われました。正論ですが、個人的にはどうやれば夢が叶うか、という応援をして欲しかったのです。が、、、そうはいきませんでした。
他にも私が出すアイディアや意見に対して、「でも、~」と言って批判する人は結構います。会社の中にもいるし、普通の雑談は出来るのですが、楽しい話になるときに限って批判してくるのです。しかも、自然に批判してくるんです。ちょっとした嫌な気持ちも積み重なると、無気力感だったり、気付けば私たちも誰かを否定し、批判していたりします。そのような人はあまり周りに置かない方がいいよ、ということも言えるのですが、なかなか仕事上であったり、かかわらないといけないことが多い間柄だったりすると「批判する人と上手に付き合う」ことが求められます。今回は、批判的な人と上手に付き合う方法をお伝えします。
1.批判してくる人の心理状態

まずは批判してくる人はどんな気持ちかを知っておく必要があります。関係性にもよるんですが、多くはあなたの足を引っ張ることを意図していません。なので、別に危害を加えたい、とか困らせたいということが目的ではないんです。批判ととるか、意見をとるか、ということになるんですが、どうしても言動だけみると邪魔しているようにしか見えません。そこで、役立つのが交流分析という学問です。
交流分析という心理学では人の言動目的は1つ。それは人から反応を貰うため、ということ。反応が良い、悪いは関係ありません。良い反応がもらえなければ、悪い反応を欲しがります。要は、全く無視されるよりは嫌われるという反応でも欲しい訳です。そして、私たちが生きていく中で必ず「人から反応がもらえる言動パターン」を取得しているということです。
極端な話ですが、子ども時代に誰かの意見に賛同したら、そうそう、となって軽い反応がもらえるという体験をします。しかし、次第に「はいはい」といって軽く流されて、意見を求められなくなったりすると、「賛同」という行為を控えるようになるかもしれません。逆に意見すると賛同よりも反応が大きかったら、その人は意見する(反対意見を述べる)ことを覚えて、次第に批判につながったりしていきます。
すべては反応が欲しいがための行動ということになります。
交流分析という心理学では人の言動目的は1つ。それは人から反応を貰うため、ということ。反応が良い、悪いは関係ありません。良い反応がもらえなければ、悪い反応を欲しがります。要は、全く無視されるよりは嫌われるという反応でも欲しい訳です。そして、私たちが生きていく中で必ず「人から反応がもらえる言動パターン」を取得しているということです。
極端な話ですが、子ども時代に誰かの意見に賛同したら、そうそう、となって軽い反応がもらえるという体験をします。しかし、次第に「はいはい」といって軽く流されて、意見を求められなくなったりすると、「賛同」という行為を控えるようになるかもしれません。逆に意見すると賛同よりも反応が大きかったら、その人は意見する(反対意見を述べる)ことを覚えて、次第に批判につながったりしていきます。
すべては反応が欲しいがための行動ということになります。
2.私たちのフィルターを整える

さて、批判をされる人はあなたから反応が欲しいためということになります。それは分かっていても、やはり、せっかく考えたことやあなたが感じたことを否定されたりすると「傷付く」のではないでしょうか。そこは心理の世界で言われている「過去と相手は変えられない。変えられるのは未来と自分」ということを思い出していただき、私たちの考え方を変えてみましょう。
では、どのようにすれば変わるのか、というと一つは知識。です。事前に批判する人のパターンを知っておきましょう。
パターンは3つ。「つかまえたぞ」というパターン。分かりやすく言うとマウントをとる方は「私の方が上だ」と思わせたいのです。というと、原因は私たちが悪い、というわけではなく、相手が上に立ちたいだけということになります。で私たちに原因がないので、そこでは悩まないとすることができます。
2つ目「キックミー」というパターン。これは嫌われたいということなので、子どもの頃の相手の過ごし方に強く関係がありますが、問題は私たちの捉え方です。このパターンはあなたに無力感を感じさせることなので、私って考えが甘いね、と言えばOKです。本当に思うことはなく、相手の目的を満たしてあげましょう。こちらも私たちに原因は無い訳なので、「傷付く」必要はない訳です。
3つ目は私たちのホメオスタシスです。このホメオスタシスとは現状維持機能です。私たちが実は変わりたくない、あまりしたくないから、という想いがあって相手の言葉の否定的な部分だけ強くインパクトが残り、否定されたから、、といって変化を躊躇うということに繋がります。
3つ目だけは私たちの心の問題なので、本当はどう感じているのかな、とまず自分のフィルターを整えておきましょう。
では、どのようにすれば変わるのか、というと一つは知識。です。事前に批判する人のパターンを知っておきましょう。
パターンは3つ。「つかまえたぞ」というパターン。分かりやすく言うとマウントをとる方は「私の方が上だ」と思わせたいのです。というと、原因は私たちが悪い、というわけではなく、相手が上に立ちたいだけということになります。で私たちに原因がないので、そこでは悩まないとすることができます。
2つ目「キックミー」というパターン。これは嫌われたいということなので、子どもの頃の相手の過ごし方に強く関係がありますが、問題は私たちの捉え方です。このパターンはあなたに無力感を感じさせることなので、私って考えが甘いね、と言えばOKです。本当に思うことはなく、相手の目的を満たしてあげましょう。こちらも私たちに原因は無い訳なので、「傷付く」必要はない訳です。
3つ目は私たちのホメオスタシスです。このホメオスタシスとは現状維持機能です。私たちが実は変わりたくない、あまりしたくないから、という想いがあって相手の言葉の否定的な部分だけ強くインパクトが残り、否定されたから、、といって変化を躊躇うということに繋がります。
3つ目だけは私たちの心の問題なので、本当はどう感じているのかな、とまず自分のフィルターを整えておきましょう。
3.自分も批判するときに気付く

批判をされると反射的に相手のことを批判しようとしている方もいます。例えば、「実は○○ってことをやろうと思っているんだけど・・」と言うと「○○は無理と思う。それよりも・・・」となると「そうかな、でも無理じゃないと思うけど、、」という会話になったりします。明らかに無理ということに対して批判していることになります。
つまり、批判する人を批判している形になります。そこで会話の中で気付くべきポイントが「でも」という言葉です。よく言われている言葉なのですが、3Dというものがあります。それが「でも」「だって」「どうせ」というものです。この3D言葉が出てきたら、自分の思考になにか良くないものが入っていると気付きましょう。まずは気付くことで、変化が生まれます。
どこに気付けばいいかという点を自分の中でしっかりと理解しておきましょう。気付いたら次は違いは悪くないと伝える練習をする必要があります。
つまり、批判する人を批判している形になります。そこで会話の中で気付くべきポイントが「でも」という言葉です。よく言われている言葉なのですが、3Dというものがあります。それが「でも」「だって」「どうせ」というものです。この3D言葉が出てきたら、自分の思考になにか良くないものが入っていると気付きましょう。まずは気付くことで、変化が生まれます。
どこに気付けばいいかという点を自分の中でしっかりと理解しておきましょう。気付いたら次は違いは悪くないと伝える練習をする必要があります。
4.違いは悪くないと伝える

どんなときに批判が起きるか、というと、今までの通り個人による価値感や考え方という要因が大きいのですが、もう少し詳しく考えると、何か違うから批判というものが起きると思われます。違いがあると批判は起きやすいのですが、全く同じであれば批判のしようがありませんから、起きないということになります。もし、批判がキツイ、しんどいということであれば、それは私たちも「違い」に対して「良くはない」という想いもあるということになります。違いがあって素晴らしい、と言うことが心から思うことができれば、そこまでキツくないはずです。なぜなら、この人はこのような考えなんだな、と素直に思えるからです。また、相手の方も同様です。違いというものに対しての容認の深さがそのまま傷付くか、平気かということになります。私たちにとって違いとは自分の可能性を広げるものとなります。
どんな人も1人では達成できないことはあります。なぜならば、生まれた時は1人では生きていけなかったからです。食べ物も取れないし、身の回りのことをやってもらわなければ病気にもなる、なので、極端な話、身の回りの世話をしてくれる人のために「合わせる」ことで私たちは生き残ってきたのです。
そのため生まれた時からなんとなく「違うと生きにくい」という考えが刷り込まれています。私たちはもう違っても生きていけます。しかも、その違いを活かしあうこともできる大人です。まずは「違い」に気付き、理解し、発展を目指せると自分にも相手にも伝えていきましょう。
どんな人も1人では達成できないことはあります。なぜならば、生まれた時は1人では生きていけなかったからです。食べ物も取れないし、身の回りのことをやってもらわなければ病気にもなる、なので、極端な話、身の回りの世話をしてくれる人のために「合わせる」ことで私たちは生き残ってきたのです。
そのため生まれた時からなんとなく「違うと生きにくい」という考えが刷り込まれています。私たちはもう違っても生きていけます。しかも、その違いを活かしあうこともできる大人です。まずは「違い」に気付き、理解し、発展を目指せると自分にも相手にも伝えていきましょう。
5.まとめ

批判に対しての考え方をまとめてみました。私が個人的に感じることは批判をする人は批判する人でエネルギーを使っているわけです。なので、そのエネルギーをどう受け取るか、というところがカギになります。そのエネルギーを攻撃と捉えれば、もちろん傷付くし、へこむし、前に進むことも妨げられますが、支援と捉えると、参考にしながら成功への確立を上げて、進んでいくと、今度はサポーターがついてきて加速していきます。
料理でいうところの包丁と一緒です。問題は使い方というところです。いきなり包丁だけ渡されても人は何をするか分かっていなければ、誤って人を傷つけるかもしれません。しかし、料理を作るぞ、食べてもらうぞ、喜んでもらうために作品を作ろう、など考えていくと包丁は傷つける道具ではなく、人の役に立つ道具になります。つまり、人のエネルギーをカタチにするのが目的です。
どのような批判も批判としてのエネルギーと受け取らず、自身の目的に活用できないか、という視点をもって批判に対して柔軟に付き合っていきましょう。
↓↓
料理でいうところの包丁と一緒です。問題は使い方というところです。いきなり包丁だけ渡されても人は何をするか分かっていなければ、誤って人を傷つけるかもしれません。しかし、料理を作るぞ、食べてもらうぞ、喜んでもらうために作品を作ろう、など考えていくと包丁は傷つける道具ではなく、人の役に立つ道具になります。つまり、人のエネルギーをカタチにするのが目的です。
どのような批判も批判としてのエネルギーと受け取らず、自身の目的に活用できないか、という視点をもって批判に対して柔軟に付き合っていきましょう。
↓↓