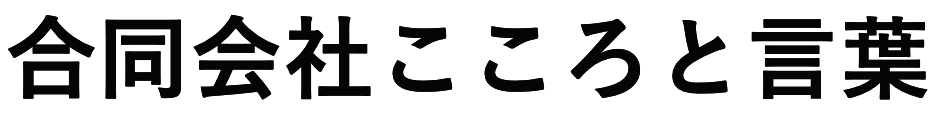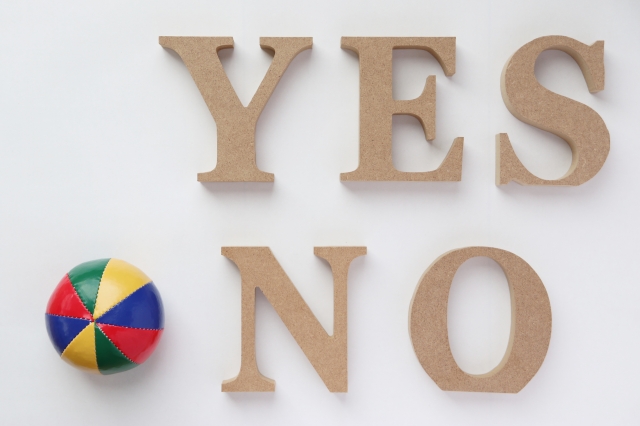今はあまり聞きませんが、私が学生の頃、日本人は「イエスマン」みたいな言葉を聞きました。なんにでも「イエス」と答えるということらしいです。日本人に括らなくとも、人によるとは思います。日本人でも「ノー」と言える人はたくさんいるでしょうし、海外でも「イエス」とつい答えてしまう人もいるでしょう。
言い方1つ
こんなことを言うと「イエスマン」に対して、あまり良い印象をもたれないような感じがしますが、共感力が高い、という表現にすると急に「イエスマン」の評価が上がったりするから不思議です。大切なのは表現の仕方と状況で良し悪しが変わってくるということなんですが、私たちはその判断をつい忘れがちです。本日はどちらかというと「ノーと言える強さ」という表現で書きます。
習慣の敵
習慣形成においてはまず、誘惑が最大の敵です。誘惑されるものを私たちの近くに置かないという原則は守らなければいけません。しかし、この情報やモノが溢れている時代にすべての誘惑を遠ざけることは困難でしょう。ダイエットであれば、コンビニでの誘惑、学習であればネットの誘惑、など。その気がなくとも「つい」ということで、身に付けたい習慣、手に入れたい結果と逆のことをしてしまう可能性があります。
療法視点
ロゴセラピーというものに逆説志向というものがあります。ざっくりとした解説なので少々解釈が異なるかもしれませんが、端的には、望まない習慣があれば、「止める」ことに意識を置かずに、敢えてやってみるというものです。
例えば、吃音。話していて、どもってしまう。どうしてもスラスラ話せないのであれば、可能な限りどもって話すことを意識するとか、虚言壁があれば、全て虚言で話すようにするとか。「止める」ではなく「敢えてする」ということなのですが、どちらかというとこれは療法的なもの。イエス、ノーで捉えると超イエスマン、という表現になるのかもしれません。
こころと言葉の習慣形成
さて、話が脱線しましたが、こころと言葉の習慣形成において、誘惑に対してはノーで攻めていきます。誘惑されたものをリスト化し、それに対してノーと言い、その数をカウントするもの。ノーと言えるものやノーと言った回数が増えていくと、私たち自身が誘惑に勝っているとカウントします。
習慣化はどのくらい続けたか、というものを○日としてカウントすることが多いのですが、逆に誘惑に勝ったというノートを作るのです。そうすることで結果的に勝ち続けたらOKとなります。ただ続けたらOKというものではなく、勝負にしてしまうのです。結局のところ、同じような感じなのですが、勝負にすることによって単に続ける、というより負けたくない、という想いが入ってきます。その方が続けやすいと思います。もちろん人の特性は入ってくるでしょうが、やり方の一つとして「誘惑に勝つノーマン」という取り組みをしてみてはいかがですか?
ノーが難しい?
最後にノーと言うのがなぜ難しいか、ということを補足しておきます、私たちは社会的な動物であるが故に、組織、あるいはチーム、コミュニティに属しています。そこから抜け出すことは安全を否定することになります。事実は違うとしても、そう感じてしまいます。それであれば、今身を置いている環境に対して「ノー」と否定することはその環境から追い出される可能性があるのです。それはとても恐ろしいことです。安全と私たちの意思を比べると安全の方をとってしまいます。それが「ノー」と言いにくい理由で、それから惰性的になんとなく合わせるという習慣が身に付き「イエス」ということになっているのではないでしょうか。
「ノーと言える強さ」という表現もありますが、「ノーと言える正直さ」を大切にいきましょう。私たちはどのような価値判断もせず、求めるものをただ追い求めていけば良いのです。その途中の道が習慣。求めるものによって一定のルールはありますが、正直にいきましょう!