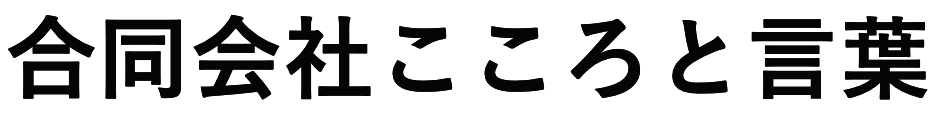「初心忘るべからず」という言葉を知っていますか?聞いたことはあったり、初心を忘れてはならないという意味で使っている方も多いと思います。何事も物事を始めた時の志を忘れてはいけない、ということで習慣にも最初の目標設定時の気持ちや志は大切だとお伝えしています。
初心忘るべからず
実はこの言葉はおよそ600年前、能を大成した世阿弥(ぜあみ)が書物に書いたのが始まりだそうです。そして、その世阿弥が言うには私たちの認識と違い、もう少し複雑で「物事にはいくつもの初心がある」ということ。子どもの頃の初心や私たち社会人の初心、そして老後の初心など。
そういった時の初心を思いだせ、というもの。
初心はどこに?
分かりやすく起業のための初心でいうと、もしかすると、最初は自由を求めて、起業をしようとしたとします。これは会社員として起業を志したときの初心ということ。
そうして、頑張って勉強して、独立していくと、今度は自由を求めてという初心がズレていきます。どういうことかというと、お客様や取引先も出てきて、責任を負うようになるのが仕事だからです。
また、自由のために頑張る途中で学びや実践をしているときには、自由を放棄しているということになります。自由のために、今の自由を放棄、という考えですね。
ここで初心に帰り、自由を求めると、責任の放棄や現状の好きなことをするようになります。・・・あれ?結局、初心に帰ると、おかしなことになっていきます。
現状の初心は捨てて、
未来から初心を見る
要はそのステージごとの初心がたくさんあるので、何処の時点の初心か、というところまで考えないといけないということです。ベースを始めたときの初心は上手くなってチヤホヤされたい、というものがありました。だから、テクニックを追い求めて、練習していましたが、次第にバンドという集団でのベースの役割や曲の調和を目指すようになりました。そして、お客さんというか観客の方が、ライブハウスに来て良かったと思えるような編曲や演出などを考えていくようになってきます。
初心に帰ろうとすると、いくつか歪みもでることがあります。大切なのはどの時点での「初心」かということです。こころと言葉の習慣化ではときどき習慣を妨げる誘惑のことを「壁」や「枠」というような表現をしています。
壁や枠を超えるとき習慣は始まる
現在の習慣と理想の習慣を比べると、現在の習慣が楽、あるいは問題は起こっていない状態なので、私たちは、現在の習慣に囲われて、守られているということになります。新しい理想の習慣はこの「壁」や「枠」を飛び越えるというもの。大体において初心を忘れないように、とすると、どの時点での初心か、という視点がない現状の視点に戻り、行動が鈍化します。
例えば、子どものために起業したから、子どもとの時間がとれないようなことがあってはならない、として、独立しても働かず、ずっと子どもと一緒にいては何もなりません。結局外に働きに出ることになり、時間の確保ができなくなります。
その初心に戻るのはいいことです。しかし、「壁」や「枠」を超えるとなると、無傷ではいられません。あるいは無傷でいるためには準備に時間がかかります。
この「子どものために」という初心に「時間軸」を組み合わせて、どこの時間を削るか、どこかで現状の習慣のバランスを崩すか、ということも念頭に置いておかなければなりません。成長をするということは確実に時間は経過しているということです。初心の時の自分と現状の自分の初心、さらに、理想の自分がもつ初心。それぞれをはっきりさせておきましょう。
習慣は行動を開始した日に始まるのではなく、壁や枠を超えた時からがスタートするのです。