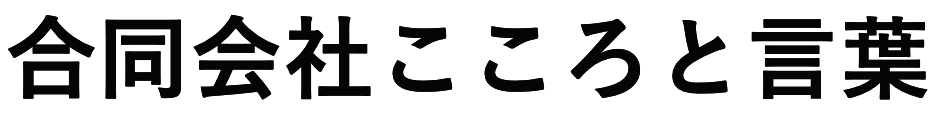心理学を学んだり、お伝えしたりしていると必ず言われることが2つあります。それが何考えているか見抜かれてそう、ということと、タイプ分析とかされてそう、というものです。もちろん心理学のイメージとしてはその2点が強いので、先入観を持たれていても構わないのですが、実際は心理学というものの歴史を考えると、相手の考えを見抜いたり、タイプを分析することが目的ではありません。そのため心理学を学んでいるからといって、世間一般でのイメージが心理家という訳ではありませんのでご安心ください。
しかし、手っ取り早い心理学の活用はやはり、「あなたは○○タイプ」といったものでしょう。そのように伝えていくと、伝えられる方も「合ってる」「合ってない」といった判断ができ、身近に心理学が感じられて、役立てることもできなくはないのですが、そこは本来の流れと違うので、そこは注意が必要です。ということで、今回はタイプ分析についての落とし穴をお伝えしていきます。
1.何のためのタイプ分析なのか?

そもそも人をタイプ分析するということをやりだしたのは誰なんでしょうか。最初の分析はカール・グスタフ・ユングが提唱した分析心理学だと思います。彼は元型という概念を作って、夢やイメージ、象徴を生み出す概念と位置付けました。今の○○タイプというものとは少し違いますが、どちらかというと本人が持っているイメージのようなものです。
元型には神話的な要素があり、トリックスターといういたずら好きな神話のキャラクターやシャドウと呼ばれるちょっとした悪役などのタイプがあります。この辺があることで、私たちは役割をしっかりと認識し、行動に理由を付けたり、行動をしやすかったりするんです。人間が縛られているルールの1つとして、基本的に「だって~だから」というものがあります。このルールがあることで私たち人間は正常であり続けることができます。因果というものです。そして人それぞれそのルールがあるため、同じ様なルールを持っている人がタイプとして分かれるようになり、安心して生活できるのです。
元型には神話的な要素があり、トリックスターといういたずら好きな神話のキャラクターやシャドウと呼ばれるちょっとした悪役などのタイプがあります。この辺があることで、私たちは役割をしっかりと認識し、行動に理由を付けたり、行動をしやすかったりするんです。人間が縛られているルールの1つとして、基本的に「だって~だから」というものがあります。このルールがあることで私たち人間は正常であり続けることができます。因果というものです。そして人それぞれそのルールがあるため、同じ様なルールを持っている人がタイプとして分かれるようになり、安心して生活できるのです。
2.タイプ分析のメリット
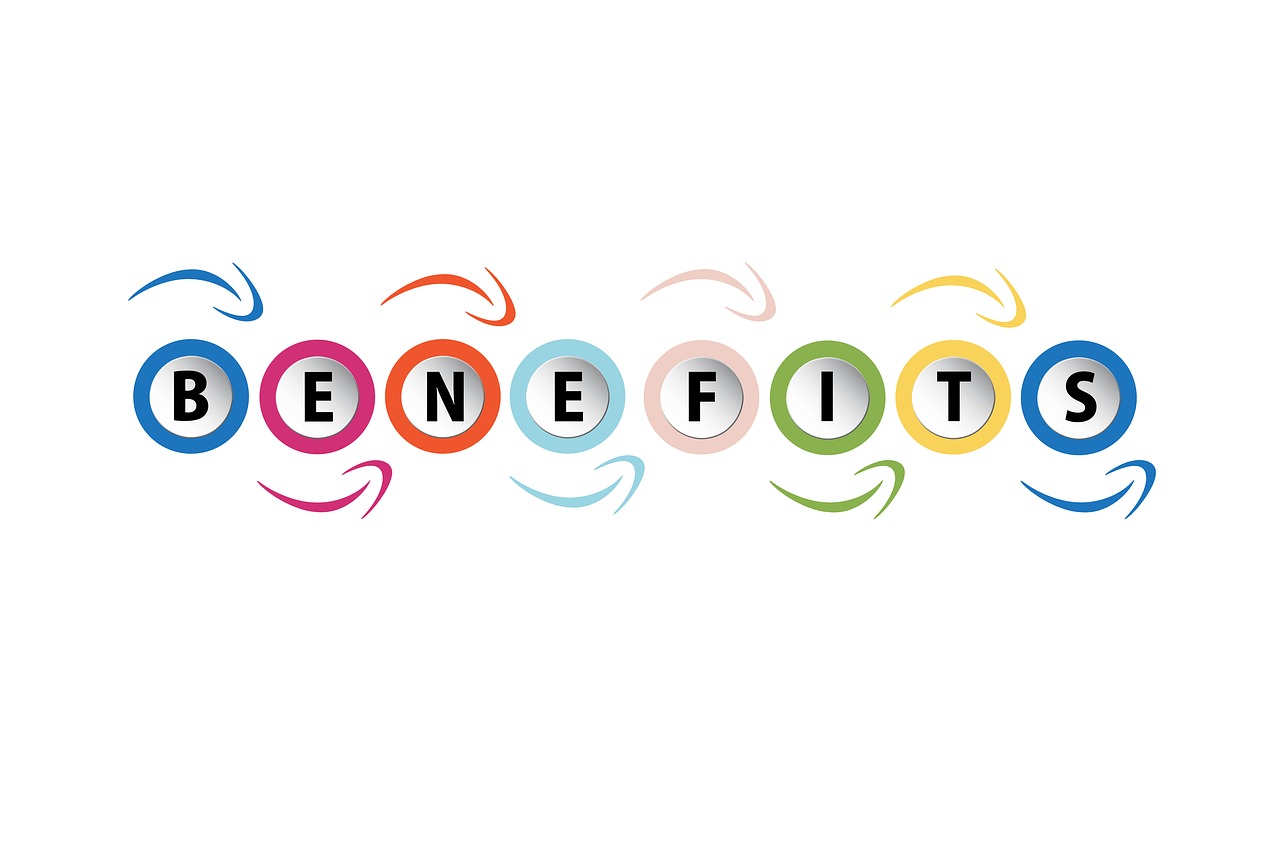
タイプ分析をすることでのメリットは行動・特性などに理由がつけられるということです。なぜそれがメリットかというと、こんな時に役立ちます。もし、私たちが頑張って努力し続けてもどうしてもできないことがあるとするとどうですか。途中でやる気をなくしそうです。もし、私たちがどの場面においても人の言うことを聞けずに、どうしても自分の我を通してしまい、場の空気を乱す存在となるとどうですか。後悔するのではないでしょうか。しかし、そのようなときも、理由がはっきりしていると大丈夫です。なぜなら私たちの中では「だって○○だから」というルールが確立されると安心するからです。
また、私たちの性格、と言われるものは2つのモノから判断されます。それは行動とその行動を引き起こす考え方です。タイプ分析はこの考え方にフォーカスが当てたものです。考え方が自分ではなくて、心理学的に分析されているものに当てはまった瞬間に私たちはふと納得するんです。私はこれでいい、と。このタイプなので、これでいいんだと。
もちろん私たちだけではなく、相手の方も付き合いやすいことになります。例えば、それぞれ分からないことになれば、お互いに何考えているか分からない、という状態よりも、Aタイプだからこうするんだ、Bタイプだから私と合わないんだと捉えることで、良い感じの距離感がとれてコミュニケーションが取れるという訳です。
また、私たちの性格、と言われるものは2つのモノから判断されます。それは行動とその行動を引き起こす考え方です。タイプ分析はこの考え方にフォーカスが当てたものです。考え方が自分ではなくて、心理学的に分析されているものに当てはまった瞬間に私たちはふと納得するんです。私はこれでいい、と。このタイプなので、これでいいんだと。
もちろん私たちだけではなく、相手の方も付き合いやすいことになります。例えば、それぞれ分からないことになれば、お互いに何考えているか分からない、という状態よりも、Aタイプだからこうするんだ、Bタイプだから私と合わないんだと捉えることで、良い感じの距離感がとれてコミュニケーションが取れるという訳です。
3.タイプ分析のデメリット

ではみんながタイプ分析をしたらみんなが幸せな生活が送れるか、というと実はそうではありません。なぜならば、タイプ分析をするということは相手を見るのではなくて、タイプを分析しようというところに意識が向くからです。簡単に言うと、人を見て知識を使うよりも、知識を実証させるためだけに人がいるという見方になるからです。「あなた」に興味がなく、分析結果が正しいか、「自分が」見る目があるか、という人と話していても、私たちは面白くありません。
例えば、あなたが誰かと会話するときにあなたの発言や考え方を知ろうとしないで、既にその人の頭の中にあるタイプを考えて「あ、この人は○○タイプだから○○に違いない」と思い込んで話すようになり、実際にあなたはそうでなくても、相手の方からは決めつけられて、窮屈さを感じたり、人として扱われていないような感じがします。タイプ分析にこだわりすぎると、人は重要性を感じられなくなり、面白くないとなります。タイプは心理学者のアドラーも言う通り、暗闇の中を照らす懐中電灯のようなものであり、光そのものではないという認識をしなければ勘違いしてしまうのです。
対象のどこを照らすのかは知識を使う人、つまり私たち自身でしかありえないので、<>私たちが知識を使うのであって、知識が私たちを踊らさせるということはないように気を付けなければなりません。
例えば、あなたが誰かと会話するときにあなたの発言や考え方を知ろうとしないで、既にその人の頭の中にあるタイプを考えて「あ、この人は○○タイプだから○○に違いない」と思い込んで話すようになり、実際にあなたはそうでなくても、相手の方からは決めつけられて、窮屈さを感じたり、人として扱われていないような感じがします。タイプ分析にこだわりすぎると、人は重要性を感じられなくなり、面白くないとなります。タイプは心理学者のアドラーも言う通り、暗闇の中を照らす懐中電灯のようなものであり、光そのものではないという認識をしなければ勘違いしてしまうのです。
対象のどこを照らすのかは知識を使う人、つまり私たち自身でしかありえないので、<>私たちが知識を使うのであって、知識が私たちを踊らさせるということはないように気を付けなければなりません。
4.心理学の使い方とは?
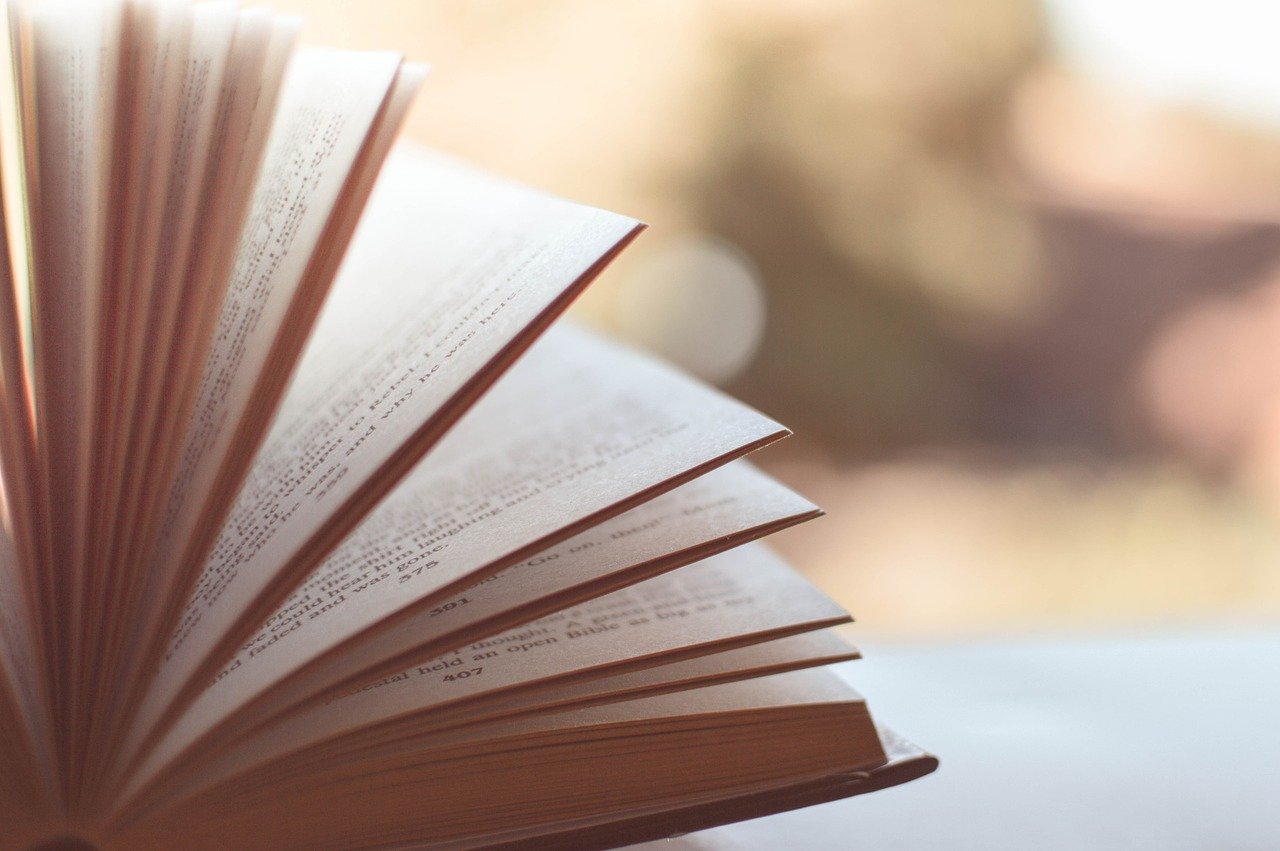
本日はタイプ分析という馴染みがある心理学を少し見てみました。心理学に関しての誤解は広がりすぎています。もちろん専門家ではない人が心理学をみると、心を見透かされそうだ、読まれそうだ、操られそうだという認識もあります。そして、その先入観から心理学を学び始めると、フォーカスが自分ではなく、どうやって相手を動かしてやろう、心理学を使って今ある悩みを解決してやろうという風になります。そうすると、さらなる思い込みが生まれ、上手く使えないという事態に陥ります。そこで、心理学を使うということは歴史を学ぶという観点で学んでいくのが良いと思います。
文明法則史学という学問もありますが、文明史には1600年の盛衰周期が存在するというもの。これはこれで「へー!」と学べるのですが、問題はこの知識をどう使うか、というものでないといけません。人間の寿命からすると1600年は長いので、忘れがちですが、全ては移り変わっています。そして、移り変わり方には大まかなルールがあります。日本なら春の次に夏、秋、冬、そしてまた春という風に季節は廻ります。心理学も基本的なルールがあります。人は心地良い環境を好み、いったん安全地帯にいくと、その慣れた環境に順応していくというもの。このパターンがあると知った上で、きちんと相手の方の話や行動を見て、どのような気持ちなんだろう、と考えながら、心理学を活用していくことが望ましいです。
そこには正解、不正解の判断は無く、「理解」があるだけです。違いを受け入れられないと成長しませんが、どこが違うか分からなければ、受け入れようもありません。そんな違いをはっきりさせ、受け入れる準備をするのが心理学の使い方だと思います。
文明法則史学という学問もありますが、文明史には1600年の盛衰周期が存在するというもの。これはこれで「へー!」と学べるのですが、問題はこの知識をどう使うか、というものでないといけません。人間の寿命からすると1600年は長いので、忘れがちですが、全ては移り変わっています。そして、移り変わり方には大まかなルールがあります。日本なら春の次に夏、秋、冬、そしてまた春という風に季節は廻ります。心理学も基本的なルールがあります。人は心地良い環境を好み、いったん安全地帯にいくと、その慣れた環境に順応していくというもの。このパターンがあると知った上で、きちんと相手の方の話や行動を見て、どのような気持ちなんだろう、と考えながら、心理学を活用していくことが望ましいです。
そこには正解、不正解の判断は無く、「理解」があるだけです。違いを受け入れられないと成長しませんが、どこが違うか分からなければ、受け入れようもありません。そんな違いをはっきりさせ、受け入れる準備をするのが心理学の使い方だと思います。
5.まとめ

タイプ分析に熱中しすぎるあまり「あなたは○○だから」という理由をつけて、人の成長幅を決めつけないようにしましょう。人は成長し、変わる生き物です。どうしても人は理由ができるとその通りに行動したりしてしまいます。これを心理学ではラベリング効果と言います。期待されている通りになるようなことです。私はやればできる、と信じていれば出来るまでやりますし、私は結局できないんだ、と信じていれば、出来ないところで行動を止めます。
タイプ分析も近い落とし穴があってそれがプラスに働いていればいいのですが、やりたくなくてもタイプ分析がそう言っているから、という理由だけでやり続けて結局は苦しんでいる人もいます。もちろん素晴らしいツールなので使ってほしいな、とは思うのですが、包丁も使い方次第。おいしい料理を作るために使うのか、傷付けるために使うのか、その辺は使い手によるものです。しっかりとどのように捉えるか、そして使うか、私たち自身をしっかりと見つめ直して使っていきましょう。
メルマガでは最新情報やプチ心理学などをGETできます(^^♪
・・・月に一度プレゼントも届くかも!!
↓↓
タイプ分析も近い落とし穴があってそれがプラスに働いていればいいのですが、やりたくなくてもタイプ分析がそう言っているから、という理由だけでやり続けて結局は苦しんでいる人もいます。もちろん素晴らしいツールなので使ってほしいな、とは思うのですが、包丁も使い方次第。おいしい料理を作るために使うのか、傷付けるために使うのか、その辺は使い手によるものです。しっかりとどのように捉えるか、そして使うか、私たち自身をしっかりと見つめ直して使っていきましょう。
メルマガでは最新情報やプチ心理学などをGETできます(^^♪
・・・月に一度プレゼントも届くかも!!
↓↓