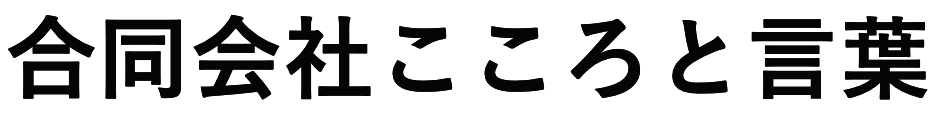不安・心配の理由
私たちは産まれてから死ぬまで実に多くのことを体験していきます。産まれたては全く分からない世界に落とされて、目も見えません。目も見えないながらに目を開け、音を聞きながら、誰かの腕の中で、生きるために母乳やミルクを求めます。しばらくすると、ぼんやりと視界に大体同じような人が映り、その人のことを安心できる母親、父親だと認識します。ここのところで「安心」できないと、自分の行動を振り返りつつ、安心できる行動を学んだりします。
例えば泣かない、騒がない、話さない、などです。それらの「学習」から個性というものを自分自身で作り上げ、何となく居心地が良い選択をして、生きていきます。

人生の途中で「生き難さ」を感じる人は今まで選んできた「居心地のいい選択」が環境の変化によって変わってきて、「生き難さ」として現れているので再度新しい選択をしなければいけません。ここで今まで培ってきた「学習」とは違う行動をとれるかどうか、というところで、その後の人生が変わってきます。
よく現状維持ではなく、成長を求めよう、向上心を持とう、という言葉を聴きますが、口で言うほど簡単ではありません。現状維持とは少なからず、今時点で生命を脅かす大きな問題は起きていないが、「なんとなく」生き難いというだけで、全く新しい行動をとり、生命を脅かすことになるのではないかという可能性の「不安」や「心配」を乗り越えられる人が取れる行動なのです。
人間の行動原理は基本的に快楽を求めるか不快を避けるかの2択とされています。行動を変えることによって得られる快楽が明確で約束されているものであれば、恐らく多くの人にとって現状維持はマイナス面が大きく、一般的にいうところの向上心を持つ、ということは容易になるでしょう。しかし、現実は行動を変えることによって、現状が壊れ、今得ている恩恵を手放し、不明確なプラスになるかもしれない可能性に賭けるということの方が苦痛です。ということで、現状維持というのが魅力的な選択であるかのように振る舞います。
さて、ここで話を「不安」「心配」に戻しつつ、人類学から見た「人間は本来的にネガティブかポジティブか」という点について考えてみましょう。単刀直入に言うと、基本的にはネガティブである、と言わざるを得ません。なぜならば、ネガティブであるから生き残れてきたからです。

生まれて目も見えないときにポジティブならまず泣きません。生まれて安心しきっていれば、きっとこう考えるはずです。「誰かが私に必要なものを与えてくれる」と。なので泣かなくとも生きられるのです。しかし、実際には泣きます。「不安」や「心配」という感情があるからという訳ではないのかもしれませんが、泣きつつ、自分の欲求を伝えます。他にも人類学の観点から見ても、ネガティブは必要な感覚です。ライオンという未知の動物に遭遇した時、ポジティブなら挨拶をして近付きます。・・・噛まれてけがを負ってしまいます。ネガティブなら注意深く観察し、安全確認ができてから対応を考え、行動します。そうすると生き残る可能性が上がります。このような意味から考えてみても、ネガティブであるから生き残れてきたのです。
また、各ご家庭や子どもの成長度合いにもよりますが、生まれて言葉を話すまでの約8,000時間の中で、周囲の情報の8割がネガティブなものであるというデータもあります。例えば、仕事頑張ってくるよ(大人になったら頑張らないといけないんだ)。泣いてるだけで身の回りの世話をされてるのは今の時期だけ(大人になったら大変なんだ)。ニュースからは○○で事件、事故が起きました(世界は不安だらけなんだ)。などの情報が無意識化に入ってきます。そうするとネガティブである方向性が強化されていき、将来に対して不安を抱くようになります。もちろん不安があるから頑張れるという側面もあります。ここではネガティブがダメ、ポジティブがいいという話ではなく、それぞれ良い面、不都合な面もあるという認識です。右手が好きか、左手が好きかと論じるようなものです。
本当の問題
しかし、本格的に問題であるのは、ネガティブであることで自分の人生の幅が狭まっているという状況です。本当の一番の問題は「それが問題であると認識している」ということです。ネガティブな思考が都合が良い人はネガティブは問題なく、現状維持が満足しか生んでいない人は現状維持が都合が良いのです。無理に変える必要はあまりありません。しかし、「不安」「心配」といった感情で本来自分がやりたいことができないというのであれば、この「不安」「心配」は付き合い方を考える必要があります。感情には、感情の5原則というものがあり、その1つとして感情はフォーカスを当てた分だけ大きくなり、返ってくるというものです。つまり、「不安」「心配」を取り除こうとすればするほど、今ある不安、心配とは別の「不安」や「心配」を連れてきて私たちに襲い掛かってくるのです。
対処の仕方

ではどうすればいいか、というとプロセスに目を向けるということ。現在の生活ではプロセスが切り離され過ぎています。当たり前にご飯を食べ、当たり前に屋根のある家で眠り、当たり前に目を覚ますことができます。安心に慣れ過ぎています。再度言いますが、良い・悪いの話ではなく、現状の分析をしているだけです。他にも、スーパーに行けば当たり前にお肉が買えます。本当はその豚肉は豚肉ではなく、牧場という場所を生きる豚という生物です。刺身は刺身ではなく、大海原を泳ぐ魚という生物です。プロセスが省かれ、結果だけ突きつけられています。そうすると「感謝」という概念が生まれにくいのです。感謝と言う概念が減っていくと、お肉に対しては生命という概念より、「腐っていないかな、お腹壊さないかな」という不安が生まれます。感謝を強要するつもりは一切ありませんが、プロセスにフォーカスを当てていくと今とは別の感情が生まれてきます。その結果「不安」「心配」という概念が減っていきます。食べ物でなくとも、明日の発表不安だな、心配だな、だったら、やってきたことを考えてみたり、やれるだけの環境を整えてくれた周囲の人の顔や言葉が思い出されたり、自分の頑張りが思い出されてきます。感情の5原則では、フォーカスを当てた感情が大きくなりますので、プロセスを知ることは今の「不安」や「心配」とは別の視点で物事を見るということです。今のモノの見方で生まれた感情とは別の感情が生まれるという構図です。

また、同じようなやり方で「現在を感じる」「学習を続ける」というやり方もあります。「不安」とは時間軸的には過去に戻って感じるものではなく、未来に向かって生じる感情です。「あれをしたらどうしよう・・・。こうなったらどうだろう・・・」。などと言った具合に、前提として「現在」は通常にあるものという考え方に立っています。とすれば、「今」にフォーカスし続ければ、「不安」や「心配」は生まれなくなります。そこで便利なのが、マインドフルネス、瞑想というものです。ここで脳科学の説明をすると長くなりますので、省きますが、どのようなやり方でも構いませんが、「今、ここ」に意識を集中します。

これは中々難しいです。考えていると、過去に怒られたことを考えていたり、明日の発表会について考えていたり、まだまだ先の将来の環境問題や人間関係の拗れについて考えていたりします。「今、ここ」のコツは、最初から考えるのではなく、意識を自分の呼吸や足のつま先の感覚などにフォーカスするようにすると、「今、ここ」を感じやすいと思います。
さらに学習をするというのも効果的です。「不安」や「心配」は意欲にもつながります。不安や心配があるから安心を求めて行動します。人間の行動原理は快楽を求めて不快を避ける、というのは冒頭にお伝えした通りです。この場合の安心が不明確だと何をしていいか分かりません。そして「分からない」という感情は不快なものです。まずは私たちにとっての安心のカタチを探し、それを言語化し、リスト化してみます。そして、それに近付くことはどのような行動をすればいいか、ということを考えてみます。そうすると、今までにない学習をしたり、今までにない行動をしたりして、明確化された安心に近付いていきます。
まとめ

まとめると不安や心配に対処するためには以下の3つということになります。
・普段からプロセスを考える癖をつけること。
・今ここに意識を向けること。
・安心を明確化し、新しい学習を始めること。
そして、本当に一番大切なのは不安との付き合い方です。このやり方をしても不安はなくなることはないでしょう。なぜなら「不安」や「心配」は私たちにとって遺伝的な視点からも、後天的な環境要因から見ても、必要であるからです。大切なことは「付き合い方」です。もし、不安に苦しめられているということであれば、是非お試しください。1人では難しければ、セミナーや新しい交流会などに参加されて、新たな視点を手に入れるだけでも解放され、理想の生活を楽しむことができるようになります。
一度しかないあなたの人生を謳歌することで、少しでも未来の子どもたちに「希望」をつなげますように!